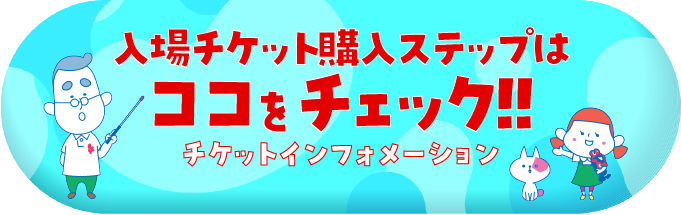能登半島地震から1年が過ぎた2025年1月初旬。高下は土台となる石材を求め、石川県志賀町を訪れていた。最大震度7を観測し、記録的豪雨にも見舞われた町内は、がれきが積み重なるなど依然として被害の爪痕が生々しく残る。「能登半島地震から一年が過ぎても次々と課題の日々。能登の未来への一歩へ協力させていただきます」。この地で創業100年を超える歴史をもつ「中島石材店」がデザインや重量設計にあいそうな石材を、「土田製材所」が型となる木材を被災した工房から一緒に探し出し、加工まで引き受けてくれた。自身も被災しながら修繕に奔走してきた日々を振り返り、ふるさとの復興の歩みを少しでも後押ししたいと願う姿に、高下はあらためて心に誓っていた。「能登の街の記憶を、再生に踏ん張る人たちの思いとともに、万博に集う世界中の人たちに伝えたい」
アルミなどの金属廃材は、金沢柿田商店の協力を得て輪島の朝市通りなどからの回収分に加え、能登の櫻田酒造店主が倒壊した酒蔵から直接届けてくれたものもあり、あわせて360kgに達した。石川県工業試験場、石川県デザインセンターと共に9ヶ月間の試行錯誤を経て、2月中旬、ようやく完成した高さ1.4mのサインスタンド。表面には大小さまざまな穴や、波打つような文様が刻まれ、約800度で溶解、精錬して砂型に流し込んだ瞬間の動き、躍動感がそのまま生かされていた。震災の記憶の継承とともに、金属の循環を描き出す。それはまるで、高下がCo-Design Challengeで目指したテーマが結実した、ひとつの工芸作品のように存在感を放っていた。
「地球上で限られた鉱物を循環し、シンプルなカタチで皆さまにお届けする」。これは、金森合金が掲げている企業理念だ。新聞印刷用のアルミ板を自動車部品に鋳造するといった産業分野にとどまらず、大手ホテルで廃棄していたアルミ缶をテーブルウェアに生まれ変わらせるなど、身近なアイテムにも製品のすそ野を広げてきた。万博に向けても、パビリオンに出展する美容室向け設備メーカーと連携し、使い捨てられるカラー剤のアルミチューブを原料にして、来場者に提供するサステナブル商品を考案中だ。「捨てることが当たり前と思われていたものを再び製造ラインのサイクルにのせていく。課題解消に向け、異業種との共創につながるコラボレーションがどんどん進むところが万博らしくて、今からワクワクしています」。高下は声を弾ませる。
高下は、金属だけでなく、工場内で生み出されるあらゆる素材、エネルギーを循環させられるサーキュラーファクトリーへの移行を思い描く。現在は、成型用の砂を再利用して水仙を育てる試みに挑む。いずれは、溶解の際に生み出される熱の活用も視野に入れている。「例えば、銭湯のエネルギー源にして地域の方々に還元していけるようになったら最高ですね」。高下は、次のフェーズに向けて走り出している。


この記事をシェアする