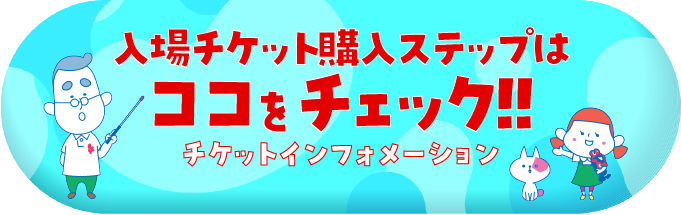モノづくりから暮らしづくりへ。「象印マホービン」は、次の100年に向けた企業の姿をこう描く。再利用可能でごみを減らせるマイボトルの使いやすさを追い求めてきたのも、その理念の表れだ。そして、たどり着いたのは外出先で手軽に利用できる「マイボトル洗浄機」。地球環境に優しい未来の利器が万博会場で披露される。
象印が、こだわり抜いた技術で生み出した商品に魔法瓶がある。ステンレスの真空二重構造で優れた保温・保冷機能を実現した。この技術を使ったマイボトルを生活に根付かせ、日常のごみを減らそうと考えた社員たちがいる。その一人が、新事業開発室長の岩本雄平だ。
新事業開発室は、創業100周年の2018年に設けられた新しい部署だ。「次の100年は、単なる『モノづくり』だけの会社ではなく、そこから脱皮して、社会や暮らしの課題を解決できる会社へと進化させたい」。岩本は新設部署の狙いについて明かす。
その地ならしは、すでに06年から進めてきた。マイボトルを「もっと持とう」「もっと使おう」というキャンペーンを展開。100周年を経て、19年には「社内ペットボトルゼロ宣言」を打ち出した。「持ち込まない」「使わない」「売らない」の3原則を徹底し、社内の自動販売機からペットボトル飲料を一掃した。
背景には、年々深刻さを増す海洋プラスチック問題がある。環境省などによると、日本のプラスチックごみは世界第2位の年間900万トンにのぼり、ペットボトルの使用量は年間200億本に達する。50年には海のごみが魚の量を上回ると予測される。日本ではリサイクルが浸透しているようにみえるが、多くは途上国に輸出され、受け入れ拒否で行き場をなくしている問題も浮かび上がる。
19年9月に象印が実施したインターネット調査では、マイボトルを持つ人の割合は7割を超えた。ところが、毎日使っている人は2割にも満たないという結果がでた。理由はシンプルだ。洗浄、中身の準備、持ち運び、という三つの手間がかかるからだ。
理由の根っこにあるのは、やはりペットボトルの存在だ。自動販売機は街のあちこちにあり、コンビニは生活インフラとして増え続けている。必要な時にすぐに買え、中身は好みにあったものを選べ、洗わなくて済む。どうしても、ペットボトルと比較され、敬遠されてしまう。
だが、必要は発明の母。「だったら、外出先で洗える機械を作ればいいじゃないか」。岩本たちの、いわば逆転の発想から、誰もみたことのない「マイボトル洗浄機」の開発が始まった。
(Vol.2へ続く)


この記事をシェアする