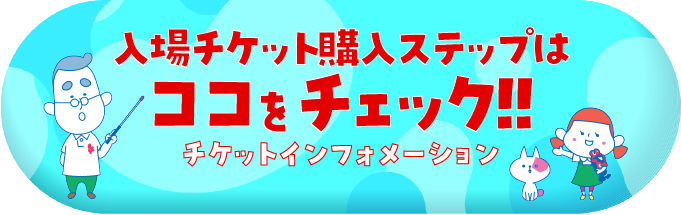素焼きされたテーブルスツールに釉薬(ゆうやく)がかけられ、1200度ほどで焼成されると全く違った景色を見せた。信楽焼の代名詞である赤茶色の焼き色「火色」の濃淡と、高温で焼くことによって光沢のある緑色に発色する釉薬「織部釉(おりべゆう)」の深い緑色が生む絶妙のコントラスト。試作品を見て丸滋製陶の今井も「いい感じで焼き上がった」と安堵の表情を浮かべた。
琵琶湖固有の魚などが模様として描かれたテーブルスツール。琵琶湖をどんな色合いで表現するか。今井は、新たに組合で配合された釉薬も使って、試し焼きを重ねて模索を続けてきた。釉薬の掛け具合を調整し、たどり着いたのが、ひと目で信楽と分かる火色の存在感をいかしつつ、穏やかにたゆたう琵琶湖を思わせる深みを持った緑色だ。テーブルトップにある琵琶湖のシルエット部分は白い釉薬を重ね掛けすることで、色合いに変化を出した。
今回万博用に開発された、陶器の破片などのリサイクル素材を練り込んだ陶土の使い勝手も上々だ。今井は「効率がよい土」だと言う。成形後の乾燥が早く、焼き上がってからの強度も増した感じがするという。資源の有効活用に加え製造エネルギーの削減にもつながるなどメリットも多く、「未来への手掛かりはできた」と今井は期待をかける。
信楽のランドマークである「登り窯」の元での陶芸体験も着々と準備が進む。テーブルスツールの模様にも使われている琵琶湖固有の魚をデジタル技術で成形した樹脂系のスタンプが、ここでも活躍する。手作りした皿やアクセサリーなどにビワコオオナマズ、ビワクンショウモなど9種類のスタンプを自由に使ってオリジナル作品を仕上げてもらう。さらに1か月後の焼き上がりを待つ楽しみもある。担当する明山陶業の石野は「万博がなければチャレンジしなかった。幅広い世代に信楽に来てもらい、ゆっくりした日常を体験してもらいたい」とほほ笑む。
信楽焼と言えばタヌキが有名だが、それにとどまらず、小物から大物まで多種多様な製品を生んできた。石野は「チャレンジし続けていくことが信楽の伝統だ」と言う。産地が一体となり課題に向き合い、社会に柔軟に対応しながら革新を重ねることで次の世代へと伝統をつなげてきた。
今井の父親の世代は、1970年の大阪万博の太陽の塔で信楽の存在感を示した。今回は、リサイクル資源とデジタル技術への挑戦で新たな創造を生み出そうとしている。山あいの静かな陶芸の里は、土と炎に向き合いながら、さらにその先の姿も追い求めていく。


この記事をシェアする