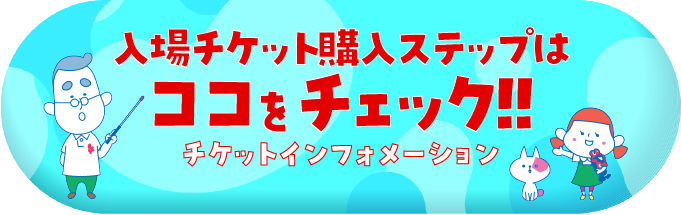プロジェクトをプロデュースする一般社団法人Design Week Kyoto実行委員会の北林は、「Co-Design Challengeを通じて、これまで組むことがなかった企業や人がつながった」と力を込める。刺繍(ししゅう)の三葉商事、家具・建具の溝川の職人技を生かすために、京都市に拠点を置くデザイン会社o-lab inc.の綾利洋、テキスタイルデザイナーTAKAKO DESIGN WORKSの田代貴子とともに、1年以上企画を練り上げてきた「作り手と使い手が共創し、思い出が持続するスツール」は、万博会場に6脚を提供する。
試作品は、高さと直径が異なる2サイズを製作した。親子連れが多いことが想定される万博会場で子どもでも腰を掛けやすいこと、座り心地の良さを重視し、低くて座面が大きい方を採用した。また、刺繍の配置などのバランスや、座面からクッション部分が取り外せるようにすることにもこだわった。伝統的な「割り楔枘(くさびほぞ)接ぎ」により組み上げられた脚部には、様々な記憶が染み込んだ古材を使用しており、取り壊される家や家具などの材料を受け継ぐことができることを提案している。北林は「スツールは座っている時間よりも、実はインテリアとして眺めている時間の方が長い」と言う。万博後に興味を持った人々がこのスツールを作りたいという際に、自身の大切な記憶を刺繍で表現したクッションを季節や気分によって交換することで、座るだけでなく眺めて思い出に浸ることができるような心の癒やしも追求した。北林は「思い出が詰まった古材や使われない生地に、記憶を意匠化し、職人の技術と思いを加えて美しくすると、大切に使う心が養えるはず」と語る。
体験企画では、ものづくり現場を訪問した人と職人が交流することを大切に考えている。北林は「工場見学」ではなく「工場訪問」と呼び、職人の技術を見るだけではなく、深い交流が可能な8人前後のグループで職人の背景にある地域の様々な場所も訪れる1泊2日のツアーを企画している。「舞鶴・丹後の歴史を調べると、最先端のものづくりを行い、自然風土と共に生きてきた街だとあらためてわかった。そういった背景の風土に触れながら、最新の機材とクラフトマンシップにあふれる三葉商事や、木に対する愛情が深い溝川への訪問やワークショップを意義付けたい」と北林は言う。
「舞鶴コース」では、三葉商事や、デザインやファッション系のものづくり企業、飛鳥時代に建てられ、国重要文化財の金剛力士像がある多禰寺(たねじ)、紀元前に創建され、産業の始祖を祭り霊水が湧く彌伽冝(みかげ)神社などを訪ね、縫製工場が手掛ける宿「SEW STAY」に宿泊する予定だ。「丹後コース」は、水・木・山をテーマとし、溝川や丹後ちりめんの生産地、日本海を一望できる大成古墳群や滝などの訪問を計画中だ。北林は「舞鶴・丹後の職人が、普段目にする製品を支えていること、そして素晴らしい技術と想いを持ってものづくりに取り組んでいることに気づいてほしい。そうした気づきで、少しでも世の中の価値観を変えていきたい」と真っすぐに前を見つめる。


この記事をシェアする