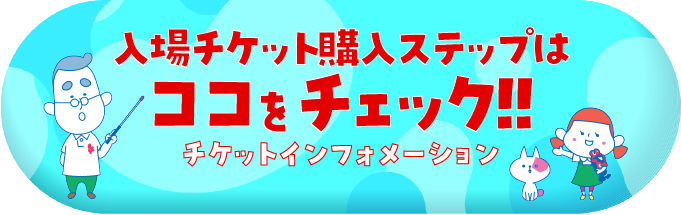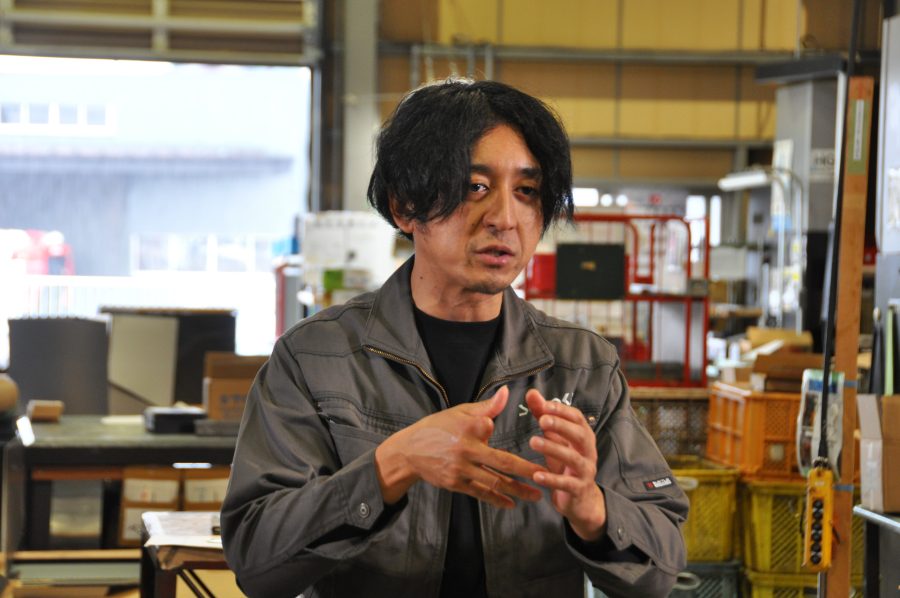
ものづくりの生産過程では、どうしても廃棄物が出る。廃棄物の再利用は多くの企業が取り組むが、新潟県燕三条のドッツアンドラインズが挑むのは、「一枚板からつくる歩留まり99%の椅子」。優れた技術を持つ企業が結集し、次の世代に引き継いでいくことを目指して、難題に取り組む。
新潟県の中央に位置する燕市、三条市をあわせたエリアは「燕三条」と呼ばれ、上越新幹線の駅名にもなっている。燕三条は金物・刃物や洋食器の生産など、ものづくりの町として知られる。
ドッツアンドラインズは、2020年に燕三条で金属加工業を営む齋藤和也が代表取締役となり、製造業の職人やデザイナー、プランナーなど多様な人材が集まり、ノウハウや技術をあわせることで、個社では実現できないものづくりへの貢献を目指す会社だ。社名のドッツは「複数の点」、ラインズは「複数の線」を意味し、一つ一つの知られざる技術力やノウハウ、企業や人々をつなげていきたいという思いが込められている。それを具現化した取り組みがある。2022年からJR東日本と連携し、燕三条駅構内に開設された地方創生型ワークプレイス「JRE Local Hub燕三条」の運営を行っている。ワークプレイス内の「燕三条こうばの窓口」では、得意分野を持つ企業とのマッチングなどに対応している。
こうした取り組みを主導する齋藤は、金属加工業に携わる中で、大きなジレンマを感じていた。脱炭素社会を目指す動きが進む中、鉄は溶かして固めるため、熱源がCO2排出につながることは避けられない。自身のものづくりで解決する方法として「出たもの、つまりは廃棄物を再利用して別の商品にするだけではなく、究極は再利用するきっかけすら作らないことが一番。〝捨てない 〟から、〝出さない 〟という発想の転換」を考えていた。
「1970年万博では、太陽の塔の背面の黒い太陽が信楽焼で作られ、地元でレガシーとなったと聞く。循環型社会など色んな言葉が語られる中、2025年万博で『廃棄物を出さない』というコンセプトのもと、燕三条の金属加工技術を結集した物品を提供することで、ものづくりのあらゆる分野で発想の転換が起こるきっかけをつくれないか。物品が何かではなく、コンセプトを残したい。そうなれば、この地域に住む子どもたちの誇りや希望となるのではないか」と齋藤は自身が抱えていた課題解決と地域への思いを重ね合わせた。
どの物品をつくるのか、またその加工過程で廃棄物、金属プレス加工で言うブランク材を出さないためには、どうすればいいのか。ドッツアンドラインズのデザイナー・後藤明寛は、その発想を折り紙から得た。「捨てないためには、折り紙のように一枚の板をそのまま使えばいい。一枚板を折りたたむことで、椅子をつくることができる」
(Vol.2に続く)


(右)デザイナー後藤明寛さん(左)代表取締役齋藤和也さん
この記事をシェアする