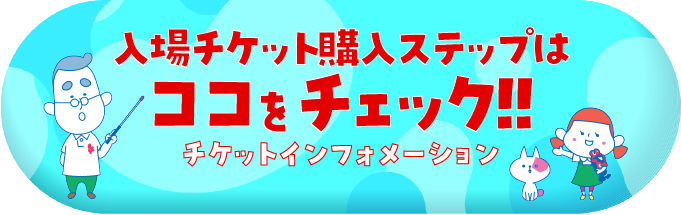丸滋製陶は1877年に創業し、創業150年近い歴史を持つ老舗だ。今井は6代目になる。主力だった火鉢から4代目の父親が傘立てやガーデンテーブルなどに幅を広げて、今の礎を築いた。父親の背中を追いかけてきた今井にとって、父の代が携わった万博もまた特別な存在だ。
信楽と万博の関係は深い。1970年の大阪万博のシンボル、岡本太郎がデザインした「太陽の塔」の背面にある「黒い太陽」は、信楽焼のタイルで出来ている。90年の「花博」では、信楽焼の陶花で飾られた噴水「花の塔(セラミック・ファンタジー)」が注目を集めた。万博開催の度に信楽は地域が連携して大舞台で、その名を高めてきた。
今回の万博会場には、リサイクル素材を練りこんだ開発陶土で焼き上げるテーブル1台とスツール4台を提供する予定だ。焼き物への加飾には琵琶湖の生き物をモチーフにすることを検討している。信楽の新しい挑戦として、最新のデジタル技術も取り入れた。ビワマス、ホンモロコなど琵琶湖固有の魚のイラストを、レーザー加工機も活用し、樹脂製の模様型を作りスツールなどに加飾していく。樹脂のため曲面にも対応でき、作業の自由度も増す。
さらに釉薬(ゆうやく)の調合にも工夫を凝らす。信楽焼の特徴的な赤茶色の焼き色「火色」をベースに、琵琶湖をイメージさせる青系色や森林を表す緑系色も使った新色で琵琶湖の豊かな恵みへのオマージュを込める。
体験企画では、万博で信楽焼の良さに触れた来場者を信楽の地にいざない、アクセサリーなどの創作を楽しんでもらう。準備を進めるのは、陶人形や食器、花器を得意とする「明山陶業」だ。9代目の石野伸也は「提供するテーブルスツールに使う同じ土と、デジタル技術を活用した琵琶湖の魚の加飾型を使って自由な作品を作ってほしい。万博の体験を信楽焼の形にして思い出にしてほしい」と期待する。伝統にとらわれず、革新性を取り入れ、新たな価値を生んできた信楽ならではの空気感。それを、この地で感じ取ってもらう。万博は絶好の機会となる、と期待する。
リサイクル陶土は、コシがあり可塑性も高く、上々の仕上がりとなった。成形には自信を持つ今井は言う。「焼き物は窯に入れたらあとは炎に委ね、窯出しするまでどんな作品になるか分からない。それが難しさであり醍醐(だいご)味でもある。それも楽しみたい」
万博で問う「これからの信楽」。先人から引き継ぎ、守ってきた「土と炎」を、次世代に託し、陶芸文化を継承する。産地の思いが大きなカタチとなって未来図を描く。
(Vol.3に続く)


この記事をシェアする